「ETFラップ」を提供する「お金のデザイン」社のセミナーレポートの続きです。
後半は、「ETFラップ」サービスの内容について。
前記事はこちら。
↓ ↓
「お金のデザイン」社主催の資産運用セミナー(その1)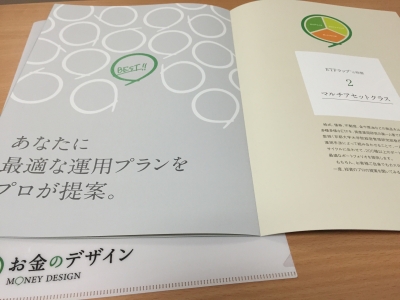
●「ETFラップ」とは?
お金のデザインでは、今のところ、セミナー参加者に限定して会員募集をしています。
今回のセミナーでは、あまり詳しい情報はなく、概略の説明のみでした。
あくまで本記事記載時点(2014年3月)で、管理人がHP等で把握できた情報です。最新情報は同社のHPなどでご確認ください。
・海外ETFポートフォリオを運用する投資一任サービス
・最低運用額は500万円以上
・運用報酬:年率1.08%(税込)
※3,000万円を超える部分は0.54%、一部解約等で預り資産が500万円を下回った場合は最低報酬54,000円/年
※購入するETFの信託報酬が別途必要(平均で約0.25%とのこと)。
・実際の売買は米国のIB(インタラクティブ・ブローカーズ証券)に口座を開設して行う
※「お金のデザイン」社との投資一任契約と、米国証券会社への口座開設が必要
※投資一任サービスなので、顧客は直接売買はできない
※Q&Aページによると、IB証券以外の対応も検討中とのこと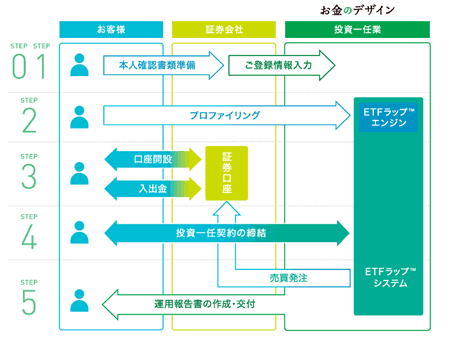
(「MONEY DESIGN お金のデザイン」サイトより)
●具体的なポートフォリオの作成方法
・プロファイリングに基づき、独自のアルゴリズムで海外ETFに基づくポートフォリオを自動作成
※対象商品は海外ETF(5,000銘柄以上)、ポートフォリオは200パターン以上
※「プロファイリング」は、サイト上で、運用方針やリスク許容度に関する質問に答えるものです。
例えば、インカム(分配)と元本拡大のどちらを優先したいか、インフレの対応をどの程度重視するか、相場が暴落した時はどうするか・・・などの質問に、当てはまるものを選びます。
試しにHP上でプロファイリングしてみたところ、確かに一瞬でポートフォリオが作成、表示されました。
数件の質問と年齢、収入、保有資産額等だけの情報で、本当に「最適なポートフォリオ」なんて作成できるの?
と思わなくもないですが、そこのアルゴリズムは同社のノウハウの肝なので、詳細は分かりません。
作成されたポートフォリオは、以下の大きく3区分に分かれています。
・グロース(株式・成長性重視)
・インカム(債券・配当重視)
・インフレヘッジ(実物資産によるインフレ対応)
それぞれの区分ごとに、組み入れるべきETF銘柄と、配分割合が表示されました。ためしに作成したポートフォリオでは、日本のネット証券では買えないETFも結構入っていました。
あわせて、そのポートフォリオの過去からのパフォーマンス推移も画面上で示されます。
セミナーでは「2007年以降」と言っていた気がするのですが、もう少し長期のデータもあるといいですね。
実際の画面はアップできませんが、イメージとしては、「わたしのindex」の「資産配分ツール」などに似た雰囲気?
実際に見てみたい方は、お金のデザイン社のセミナーに参加すると、HPログイン用の「招待コード」が配布されますので、参加してみてください。
(勧誘などは一切ありませんでしたので大丈夫です)
●「ETFラップ」は普及するか?
資産残高の1%を毎年負担しても、金融資産の運用は専門業者にお任せして、自分は仕事や趣味に時間を使いたい、という人や、海外の証券会社でないと買えない多数のETFにアクセスしたい、という人には、このサービスは検討してみる価値はあるでしょう。
ただ、(保有資産のうち一部のサテライト商品とかではなく)運用資産全額に対して、毎年1%のコスト負担は長期ではかなり効いてきます。
1,000万円預ければ、信託報酬以外に毎年10万円、10年で100万円(+消費税)です。
例えば、投資一任サービスの代表であるラップ口座の手数料をみると、大和証券のファンドラップの場合、年間1.512%(税込、5,000万円以下の場合)です。
これらよりは低いですが、「ポートフォリオ作成は全て自動化、サービスの提供や運用状況の管理も全てネットなので大きくコスト削減」という割には、年1.08%はすごく安い、とも言えません。
また、品ぞろえの点ですが、長期分散投資をしたい普通の人にとって、「5,000以上のETF銘柄」「200パターン以上のポートフォリオ」もの膨大な選択肢が果たして必要かどうか?は意見が分かれると思います。
国内で買えるインデックスファンドや国内外ETFも充実してきていますし、海外の証券会社に比べて品ぞろえが少ないとはいっても、ベーシックな資産クラスは全てカバーされています。
ちょっと勉強すれば、それほど手間いらずで、低コストな分散ポートフォリオを自分でも組めてしまうので、特に、ネット証券で自己解決できる現役世代にこのサービスが広まるかといえば難しい面があると思います。
現状では、どちらかというと、年齢の高めの既存のファンドラップの顧客層と重なる部分がターゲットかもしれません。
ただ、「任せる運用」を日本でも広めようという理念は評価できますし、運用報酬をもう少し低めにするか、最低運用額を引き下げれば、すそ野も広がる可能性はあると思います。